広告制作やSNS運用をしていると、「この表現は大丈夫かな?」と悩む場面は少なくありません
特に医薬部外品に関しては、「予防」と「治療」の境界線が非常に重要です。ちょっとした言い回しが規制に触れる可能性があり、行政からの指導対象になってしまうこともあるのです。
今回は「化粧品等の適正広告ガイドライン(2020年版)」の中でも、特に現場で間違いやすい 『○○を防ぐ』表現ルール について、実務で役立つ形で解説していきます。
1. 医薬部外品広告の基本原則
まず大前提として、ガイドラインの「医薬部外品の効能効果の表現の範囲」では、承認を受けた効能効果の範囲を超えた表現をしてはならない と定められています。
これは薬機法第66条(誇大広告等)や、医薬品等適正広告基準第4の3(1)を根拠にしています。
医薬部外品は「人体に対する作用が緩和なもの」と定義されており、医薬品のような「治療効果」を謳うことはできません。
たとえば、ニキビ治療薬のように「治す」「改善する」と書くのはアウトですが、「にきびを防ぐ」といった予防的な表現は承認されている範囲内であればOKなのです。
2. 「○○を防ぐ」表現とは?
その中で特に広告の現場で抵触しやすいのが 『効能効果が○○を防ぐの場合の表現』 です。
この規定は、医薬部外品が承認を受けた「予防」の効果を広告する際に、消費者が誤解しないようにするためのルールです。
例えば「にきびを防ぐ」と承認されている製品について、広告で「にきびに」と書いてしまうとどうなるでしょう?
消費者の多くは「にきびを治す」「改善する」というニュアンスを連想してしまいます。
これは承認範囲を超える治療的効果を暗示してしまうため、規制に抵触する可能性が高くなります。
そのため、ガイドラインでは「承認された『防ぐ』という言葉を正しく使いましょう」と明確にルール化しているのです。
3. 原則ルール:必ず「防ぐ」と書く
『効能効果が○○を防ぐの場合の表現』についてのルールの原則はシンプルです。
「○○を防ぐ」と承認されている場合、単に「○○に」とは書けない
具体例を見てみましょう
| NG表現 | OK表現 |
| にきびに | にきびを防ぐ |
| フケ・かゆみに | フケ・かゆみを防ぐ |
| 口臭に | 口臭を防ぐ |
なぜこのように厳格なのかというと、広告は短いキャッチコピーやビジュアルで消費者に印象を与えるため、少しの言葉の違いでも「治療効果がある」と誤解されるリスクが高いからです。
4. 例外ルール:承認効能が明確に別記されている場合
ただし、例外も用意されています。
それは 承認された効能効果が明確に記載されている場合は、補足的に表現を工夫してよい というものです。
例えば
- 「この化粧水は『にきびを防ぐ』効能で承認されています」
- その上で、「にきび対策に」と補足するのはOK
つまり、「本来の効能効果がしっかり伝わっている」という前提があれば、表現の幅が少し広がるのです。
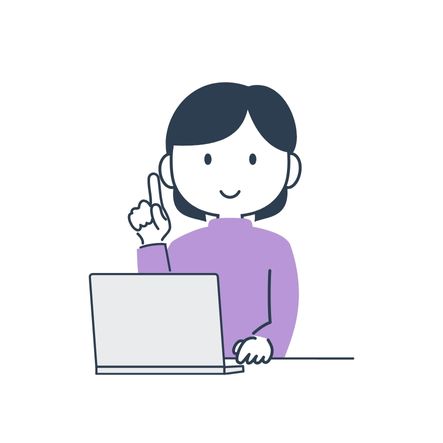
この例外規定は、広告実務において一定の柔軟性を持たせるための仕組みと言えますね。
5. ガイドラインと基準の一貫性
ガイドラインだけでなく、「医薬品等適正広告基準」やその解説でも同じ考え方が示されています。
『○○を防ぐ』という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に『○○に』等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない。
つまり、複数の規制文書で繰り返し強調されているということは、それだけ違反事例が多いという裏返しでもあります。広告制作に関わる人は必ず理解しておくべきルールです。
6. 実務で注意すべきポイント
広告現場でよくある注意点を挙げます。
キャッチコピーでの短縮に注意
広告やパッケージでは、できるだけ短くインパクトのある言葉を使いたくなります。
しかし、キャッチコピーの省略や強調は一瞬で消費者の目を引く反面、誤認を招きやすいので、承認効能そのものを正確に伝えることが基本です。
SNS広告やインフルエンサー投稿も同じ
SNS広告やインフルエンサーの投稿は、文字数やスペースが限られるため、つい短縮表現や強調表現に頼ってしまいがちです。
しかし、InstagramやTikTokといった媒体でも、広告規制のルールは一切変わりません。
「にきびに効く」といった誤認を招く表現はNGですし、短い動画や投稿であっても承認効能の範囲を逸脱してはいけません。
むしろSNSは拡散性が高いため、誤解を招く表現は一気に広がり、企業の信頼を大きく損なうリスクがあります。
必ず承認された効果をベースに
医薬部外品の広告表現を考える際は、必ず「承認された効能効果」を出発点にしなければなりません。
例えば「にきびを防ぐ」と承認されている場合、広告でもまずそのままの文言を使うことが大前提です。
そのうえで、補足的に「にきび対策に」といった表現を添えることは認められるケースがあります。
重要なのは、承認効能がはっきりと明記されていることです。
消費者に誤った期待を抱かせないよう、「防ぐ」「予防」というニュアンスを正しく残す工夫が必要です。
消費者の受け取り方を意識
広告表現をリーガルチェックする際に忘れてはいけないのが「消費者の受け取り方」です。
形式的には承認範囲内の言葉を使っていても、消費者が「治る」「改善する」と誤解してしまう可能性があるなら、その表現は不適切です。
法律的な観点だけでなく、一般の人がどのように読み取るかを想像することが、健全な広告作成の第一歩となります。
結局のところ、消費者が安心して商品を選べるかどうかが最も大切なのです。
まとめ
- 医薬部外品の広告は「予防」が目的であり、「治療」と誤認される表現は禁止
- 「○○を防ぐ」効能の伝え方を明確に定めた重要なルールがある
- 原則:「防ぐ」を省略して「○○に」と書くのはNG
- 例外:承認効能が明確に記載されている場合のみ、補足的に「○○対策に」といった表現が可能
広告担当者やライター、インフルエンサーにとっては少し窮屈に感じるかもしれません。しかし、正しい表現を守ることが、消費者に誤解を与えず信頼を築く第一歩です。
ぜひこの記事を参考に、「誤解のない、正確で魅力的な広告表現」を意識してみてください。
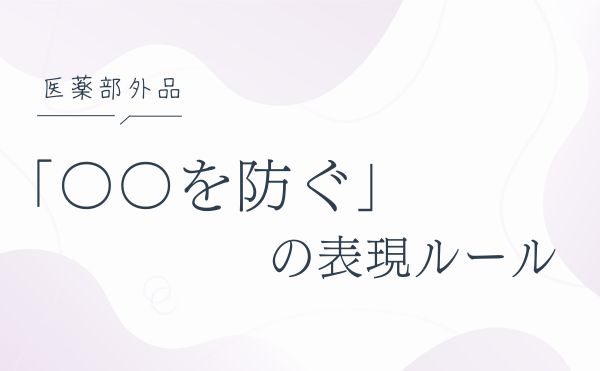
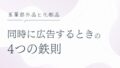
コメント