近年、ソーシャルメディアの普及やインフルエンサーマーケティングが普及し、商品紹介の方法も多様化しています。
特に化粧品の広告では、ユーザーの「体験談」が消費者の購買意欲を強く刺激するため、「こんな効果があった!」「劇的に変わった!」といった声が溢れがちです。
しかし、実は化粧品において、体験談による効能効果や安全性の保証をうたうことは、日本の法律で厳しく規制されており、違反となる可能性が高いことをご存知でしょうか?
この記事では、なぜ化粧品の体験談が規制の対象となるのか、そして具体的にどのような表現が問題となるのかを詳しく解説します。
なぜ体験談による化粧品の効能効果・安全性の保証はNGなのか?
化粧品の広告において体験談が規制される主な理由は、「作用の緩和性」と「消費者の誤認防止」にあります。
1. 化粧品の作用は「緩和」である
日本の法律では、医薬品と化粧品は明確に区別されています。医薬品が疾病の診断、治療、予防を目的とするのに対し、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つこと」を目的とし、人体に対する作用が「緩和なもの」と定義されています。
そのため、化粧品に期待されるのは「穏やかな働き」であり、医薬品のような「治療」や「劇的な改善」といった効果は認められていません。
体験談で「まるで病気が治ったようだ」「体質が劇的に変化した」といった表現が使われると、本来の化粧品の定義を超える効果があると誤解を招くことになります。
2. 体験談は「客観的な裏付け」とはなりえない
化粧品の効果は、個々人の肌質、生活習慣、使用方法など多くの要因によって異なります。そのため、ある一人の体験者の感想が、全ての人に当てはまるわけではありません。
日本の「医薬品等適正広告基準」では、化粧品等の効能効果または安全性に関する愛用者の言葉、使用経験または体験談(タレントや一般の利用者によるもの問わず)は、客観的な裏付けとはなりえないと明記されています。
つまり、化粧品の効能や安全性を、タレントや一般の人の体験談で裏付けることはできないと定めています。
このような表現は、消費者に化粧品の効果や安全性について誤解を与えるおそれがあるため、原則として行わないこととされています。
3. 消費者保護の観点から「誤認」を防ぐ
広告の目的は、消費者に適切な情報を提供し、自主的かつ合理的な商品選択を促すことです。
しかし、体験談は個人の主観に基づいているため、事実と異なる認識を与えたり、実際よりも著しく優良であると誤認させたりする可能性があります。
特にインターネット上の口コミサイトや著名人のブログにおける「ステルスマーケティング」(実際は広告宣伝であるにもかかわらず、個人の自発的な表明であるかのように見せる行為)は社会問題となっており、消費者を誤認させるおそれがある場合、虚偽誇大表示等に該当する可能性があります。
消費者は、口コミ情報を中立・公正な第三者によって書かれたものと認識しやすいため、その影響は通常の広告よりも大きいと考えられます。
4. 免責表示があっても「誤認」を打ち消せない
広告で「個人の感想です」「効果を保証するものではありません」といった免責表示を付記するケースが見られます。
しかし、これらの表示があっても、広告内容全体が消費者に誤解を与える場合は、虚偽誇大表示等に該当するかどうかの判断に影響を与えません。
広告全体から、あたかもその商品に特定の効果があるように消費者が認識してしまうにもかかわらず、実際にはそのような効果がない場合、それは虚偽誇大表示とみなされます。
どんな表現が化粧品の効能効果・安全性の保証に当たるのか?
化粧品の効能効果や安全性を保証する表現は、直接的なものだけでなく、暗示的なものも規制の対象となります。
1. 医薬品的な効果や劇的な変化を暗示・標ぼうする表現
化粧品は、疾病の治療や予防を目的とした効果を標ぼうできません。
また、身体の構造や機能に影響を及ぼすような、医薬品的な効能効果を暗示することも問題となります。
- 「シワ専用美容液、シワを直す、シワを取り去る」
- 「エイジングケアで目覚めればシワ、タルミすっきり!」
- 「肌細胞に直接働いてシミ、しわ、たるみにエイジングケア」
- 「お顔がホッソリ!顔が小さくなりました。」
- 「肌の老化と戦う抗酸化成分○○を配合」
- 「身体の特定の部位(目、関節、脳等)の健康を維持する」 (※これは健康食品の例ですが、化粧品にも同様の原則が適用されます。)
2. 最大級の表現や、効果の速効性・確実性を保証する表現
「最高の効果」「無類の効果」「世界一」といった最上級の表現や、効果が必ず現れるかのような表現も、客観的に立証困難なため虚偽誇大表示となるおそれがあります。
- 「比類なき安全性」「絶対安全」
- 「最高のききめ」「無類のききめ」
- 「効き目№1」「安全性№1」 (※売上No.1は客観的根拠があれば認められる場合があります)
- 「すぐ効く」「飲めばききめが3日は続く」
- 「誰でも簡単に」「短期間で驚きの変化が実感できます」
3. 使用前後(ビフォーアフター)の写真やイメージ図
使用前後の写真や図は、メーキャップ効果などの物理的な効果を表現する場合に限り認められますが、それが事実の範囲内であり、効果や安全性の保証表現とならないように注意が必要です。
- 「乾燥による小ジワを目立たなくする」の効能を有する化粧品を使用した肌の使用前後の写真等
- 「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」が承認効能である薬用化粧品の使用前後の写真・イメージ図等
- 歯のホワイトニングで、歯みがきによる物理的効果を超えた「漂白作用」や「半永久的な白さ」を暗示するビフォーアフター写真
- 肌の色自体がだんだん白くなることを示唆する美白・ホワイトニングのビフォーアフター写真
4. 承認された効能効果の範囲を逸脱した表現
化粧品には、医薬品医療機器等法で定められた56項目(またはそれに準ずるもの)の効能効果の範囲しか認められていません。
薬用化粧品(医薬部外品)についても、それぞれ承認された効能効果の範囲があります。
これらを超えた効果を標ぼうすることはできません。
- 「肌が明るくなったのでビックリしました。」(※「皮膚を清浄にする」や「肌を整える」などの範囲を超える場合)
- 「眼の下の小ジワにうれしい変化が!」
- 「キメが細かくなって、チョット嬉しくなるくらい効果が実感できました。」
- 「こんなにハリがでるなんて。」
- 「まつ毛を育てる美容液です。」「まつ毛が伸びます」(※化粧品では育毛の標ぼうは一切不可)
- 「歯肉炎、歯周病の予防に」(※歯みがき類が化粧品の場合、これは医薬部外品の効能)
5. 専門家や公的機関の推薦を暗示する表現
多くの人の認識に相当の影響を与える可能性がある人物や団体等が、医薬品等を推薦する表現は禁止されています。
- 医薬関係者(医師、薬剤師等)
- 理容師
- 美容師
- 病院
- 診療所
- 薬局
- 学校
- 学会
- 公務所
上記のような専門家や公的機関が製品を指定、公認、推薦、指導、または選用している旨の広告を行うことはできません。
- 「皮膚科専門医も奨める」
- 「○○美容研究所推薦」
- 「厚生労働省認可」「消費者庁承認」
- 「○○大学との共同研究」(※化粧品の場合、これは医薬関係者等の推薦に該当し、または効能効果の逸脱を招く可能性がある)
まとめ
化粧品広告における「体験談」は、その表現が客観的な事実に基づかず、消費者に製品の効能効果や安全性について誤解を与えるおそれがある場合に、虚偽誇大表示として規制の対象となります。
たとえ「個人の感想です」といった免責表示を付記しても、広告全体の印象が誤認を招くものであれば、規制を免れることはできません。
広告を制作する際には、化粧品に認められている効能効果の範囲を正確に理解し、「事実に基づく適切な情報提供」を最優先することが重要です。
特に、身体の変化や疾病の改善を暗示するような表現は、消費者の誤認を招きやすいため、細心の注意を払う必要があります。
企業やインフルエンサーの皆様は、ぜひこの情報を参考に、消費者に対し誠実で信頼性の高い広告表現を使用するようにしましょう。

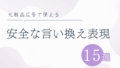
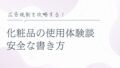
コメント