美容広告において、製品の「香り」は消費者の購買意欲を高める重要な要素です。
しかし、香りの表現には薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)をはじめとする厳格な広告規制が存在します。
意図せず規制に抵触しないよう、今回は「香り」に関する広告表現のポイントを徹底解説します。
「香り」についての広告規制のポイント
「香り」に関する具体的な広告表現の可否について見ていきましょう。
1. 香りの「マスキング効果」は表現可能
化粧品の効能効果の範囲として、「芳香を与える」という表現が認められています。
また、「香りにより不快臭を抑える」という表現も可能です。
これらは、香りが持つ本来の「匂いをつける」「不快な匂いを覆い隠す」といった物理的・感覚的な効果を表現するものであり、化粧品の「身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」という定義の範囲内とされています。
2. 「リラックス」など、精神や身体に直接作用する表現はNG
化粧品は「人体に対する作用が緩和なもの」と定義されており、医薬品のように「疾病の診断、治療又は予防」や「身体の構造又は機能に影響を及ぼすこと」を目的とするものではありません。
そのため、香りが直接的に精神や身体の機能に作用するかのような表現は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するため認められません。例えば、以下のような表現は原則として禁止されます。
- 「ストレスを軽減する香り」
- 「心を落ち着かせるアロマ」
- 「深いリラックス効果で安眠を誘う」
「肌の疲れをいやす」といった「疲労回復的表現」も化粧品には認められていません。
化粧品は薬理作用による効能効果を表現できないためです。
3. 「空間」や「気分」を指す表現のニュアンス
ただし、表現のニュアンスによっては「リラックス」という言葉が使用できる場合があります。
重要なのは、その効果が人体の生理機能に直接作用するものではないと消費者が認識できることです。
例えば、香りが「空間の雰囲気」に影響を与えることを示す場合は、許容される可能性があります。
- 「リラックス空間に」:香りが漂うことで、その場の雰囲気が落ち着く、といった意味合いであれば認められる可能性があります。
これは「清涼感を与える」「爽快にする」といった、薬機法上の効能効果に直接は含まれないものの、事実に基づき、かつ効能効果や安全性を保証する表現とならない範囲で認められる使用感や物理的な効果の例と類似しています。
あくまで「雰囲気」といった感覚的な表現に留め、治療的、生理機能改善的、または医学的な効果を暗示しないよう注意が必要です。
広告表現におけるその他の注意点
香りの表現に限らず、美容広告全般において以下の点に留意しましょう。
- 効能効果や安全性の保証表現の禁止: 「これさえあれば」「安全性は確認済み」など、効能効果や安全性を保証する表現は禁止されています。
- 最大級の表現の禁止: 「最高の効果」「世界一」といった最大級の表現は認められません。ただし、客観的調査に基づく「売り上げNo.1」などは、出典を明記すれば認められる場合があります。
- 使用体験談の禁止: 効能効果や安全性に関する使用体験談(タレントや一般人問わず)は、客観的裏付けとならないため禁止されています。ただし、使用感や香りのイメージに関する感想は、事実に基づき、過度な表現や保証的な表現とならない範囲で認められます。
- 使用前・後の写真や図面の制限: 承認外の効能効果を連想させるものや、効果・安全性の保証となる使用前後の写真等は認められません。メーキャップ効果を示す場合は使用できますが、事実の範囲内に限られます。
まとめ
美容広告における「香り」の表現は、「芳香を与える」「不快臭を抑える」といった化粧品本来の機能の範囲内で、事実に基づいた感覚的な表現に留めることが重要です。
精神や身体の機能に直接作用するような医薬品的な効能効果を暗示する表現は厳しく規制されますが、「空間の雰囲気づくり」といった非治療的なニュアンスであれば、表現の可能性も広がります。
広告を作成する際は、消費者への正確な情報提供を常に心がけ、最新の法規制やガイドラインの趣旨を理解し、適切な表現を用いるようにしましょう。
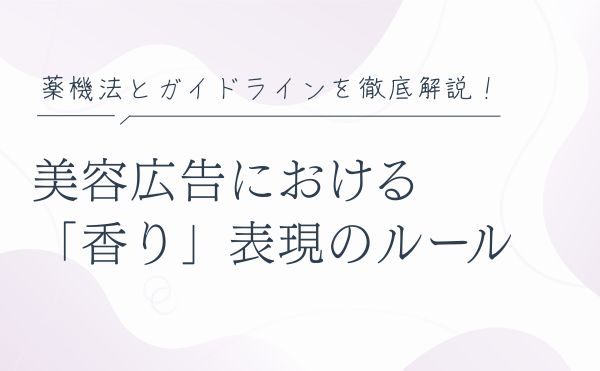
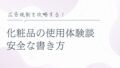
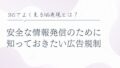
コメント