はじめに
SNSで商品を紹介するインフルエンサー投稿。
一見「個人の感想」と思われがちなこれらの投稿にも、薬機法や景表法が関係してくる場合があります。
特に美容・健康系の商材を扱う場合は、広告と判断された瞬間から厳しいルールの対象になります。
では、どのような投稿が「広告」とみなされるのでしょうか?
この記事では、広告該当性の基本と、実際にどのような投稿が広告に該当するのかをわかりやすく解説します。
SNS投稿が「広告」と判断される条件とは?
薬機法などの規制は、「広告」に該当するものが対象です。
つまり、広告に該当しなければ基本的に規制の適用外ということになります。
では、広告に該当するかどうかの基準は何でしょうか?
実は、厚生労働省が示す「3つの要素」が判断の軸になります。
【広告と判断される3つの要素】
化粧品等の適正広告ガイドライン※1では、次の3つすべてに該当する場合、広告とみなされます。
- 顧客を誘引する意図があること(誘引性)
→ 購入や申し込みを促すような表現が含まれているか - 特定の商品やサービスの名称などが明示されていること(特定性)
→ 何の商品を紹介しているのかが明確になっているか - 一般人が認知できる状態であること(認知性)
→ 不特定多数が閲覧できる状態にあるか(SNSの公開投稿など)
化粧品等の適正広告ガイドラインとは?
化粧品等の適正広告ガイドラインは、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)を踏まえて、化粧品や医薬部外品、石けんなどの広告に特化して作られた指針です。
厚生労働省の監修のもと、業界団体(日本化粧品工業連合会など)が策定しており、誇大広告や虚偽表示を防ぐための具体的な表現基準を示しています。
「広告とみなされる条件」や「効能効果の範囲」「比較・体験表現の注意点」などが定められ、企業や販売者が消費者を誤認させないためのルールブックの役割を果たしています。
「事業者性」についての補足
上記ガイドラインでは「事業者の意図に基づくもの」という要件(事業者性)は明記されていません。
しかし、消費者庁や公正取引委員会が示す一般的な広告判断基準では、事業者性も重要な要素とされています。
これは、個人が自発的に投稿しただけなのか、それとも事業者から依頼・報酬(現物含む)を受けたうえで行ったのかによって、広告該当性の判断が変わるためです。
特にステマ規制(景品表示法改正)では、事業者性がある場合は広告表示義務(#PR など)が必要となります。
つまり、化粧品等の適正広告ガイドラインに従う場合でも、法令上のリスクを避けるためには「事業者性」も併せて確認することが望ましいと言えます。
実際に広告となる投稿と、ならない投稿の違い
広告該当性を判断するときは、先ほどの3要素(誘引性・特定性・認知性)に加え、実務上は「事業者性」も確認します。
ここでは、具体例を挙げて見ていきましょう。
- アフィリエイトリンクへの誘導
例:「詳しくはこちらから」などの文言と一緒に、アフィリエイトリンクを設置している場合 - 企業からの案件
報酬(現金や現物)が発生する投稿は、事業者性が認められ広告となります - 自社の宣伝アカウントによる投稿
企業や事業者が自社商品のPR目的で運用しているアカウントからの投稿は、基本的に広告とみなされる可能性が高いです
アフィリエイトリンクへの誘導
アフィリエイトリンクを設置し、そのリンク先の商品やサービスの購入を促す投稿は、ほぼ確実に広告とみなされます。理由は明確で、読者を購入ページへ誘導する意図(誘引性)があり、特定の商品名やブランド名(特定性)が明示され、かつ一般の閲覧者が認知できる状態(認知性)で公開されているためです。
さらに、リンク経由で発生する成果報酬が投稿者に支払われる仕組みは「事業者性」を裏付ける要素となります。
このため、薬機法や景表法だけでなく、ステマ規制に基づく「広告である旨の明示」義務が生じ、適切な表記や表現管理が必須となります。
企業からの案件
企業から依頼を受けて報酬(現金や現物)を得て行う投稿は、広告に該当します。
「商品をお渡しするので、実際に使ってクチコミを書いてください」
といったものも、報酬(商品)を受け取っていることになります。
ここでのポイントは、報酬の有無が「事業者性」を強く裏付けるという点です。
たとえ文章や画像に直接的な販売リンクがなくても、依頼主の商品やサービスをPRする目的で作成されたコンテンツは、誘引性・特定性・認知性の条件を満たしやすく、広告と判断されます。
特に美容や健康関連では、薬機法・景表法に加えて、ステマ規制による広告表示義務が課されます。
依頼内容が口コミ調でも「案件であること」を明示しなければ、規制違反になるリスクがあります。
自社の宣伝アカウント
企業や個人事業主が、自社製品やサービスの宣伝を目的として運用する公式アカウントからの投稿は、ほぼすべてが広告として扱われる可能性があります。なぜなら、アカウント自体が販促活動のために存在しており、投稿一つひとつが販売促進につながる意図(誘引性)を内包しているからです。
商品名やサービス名(特定性)も明示されることが多く、フォロワーや一般閲覧者が自由に閲覧できる(認知性)ため、広告該当性が極めて高くなります。
そのため、表現は常に法令に沿ったものである必要があり、定期的なリーガルチェックが推奨されます。
なお、アフィリエイトや企業案件において、万が一規制に抵触する広告表現を行った場合、原則として法的責任は投稿者ではなく依頼主である企業に課せられます。
そのため、企業側は薬機法や景表法などの規制を理解し、安全性の高い表現で投稿を作成できる発信者を強く求めています。
つまり、広告表現のルールを正しく把握していることは、発信者としての信頼性や案件獲得率を高める大きな武器となります。
- 個人が情報を発信しているだけの投稿
案件でもなく、アフィリエイトリンクもなく、自社商品の宣伝アカウントでもない場合
例:趣味で化粧品レビューを書いている個人ブログ(広告収入も案件もなし)
個人が情報を発信しているだけの投稿
案件でもアフィリエイトでもなく、自社商品の宣伝アカウントでもない個人の投稿は、基本的に広告には該当しません。
例えば、趣味で化粧品の使用感をブログにまとめている場合や、購入品紹介をSNSに載せる場合がこれにあたります。この場合、読者を購入に誘導する意図がなく、報酬の発生もしないため「事業者性」が欠けます。
ただし、広告でなくても「この化粧品でシミが消えた」など効果効能を断定的に表現すると薬機法違反になる恐れがあります。広告該当性が低くても、表現の根拠や法令遵守の意識は常に必要です。
投稿パターン別・広告&法令リスク度合いチャート
| 投稿パターン | 広告該当性 | 主なリスク | リスク度(★5段階) |
|---|---|---|---|
| アフィリエイトリンクへの誘導 | 高い | 薬機法・景表法・ステマ規制(表示義務) | ★★★★★ |
| 企業からの案件投稿 | 高い | 薬機法・景表法・ステマ規制(表示義務) | ★★★★★ |
| 自社の宣伝アカウント投稿 | 高い | 薬機法・景表法・不当表示防止 | ★★★★★ |
| 個人が情報を発信(案件・アフィリエイトなし) | 低い | 虚偽誇大・効能効果表現による薬機法違反 | ★★☆☆☆ |
| 口コミ・体験談のみ(広告要素なし) | 低い | 表現によっては薬機法対象となる可能性 | ★☆☆☆☆ |
リスク度
★★★★★ ─ アフィリエイトリンク/案件/自社宣伝アカウント
★★★★☆
★★★☆☆
★★☆☆☆ ─ 個人発信(案件・アフィリエイトなし)
★☆☆☆☆ ─ 口コミ・体験談のみ
まとめ
この記事では、化粧品等の適正広告ガイドラインに基づき、広告とみなされる条件(誘引性・特定性・認知性)と、事業者性の重要性について解説しました。
アフィリエイトリンク、企業案件、自社の宣伝アカウントは広告該当性が高く、薬機法・景表法・ステマ規制の対象となります。
一方、個人が案件や報酬なしで発信する投稿は広告には該当しませんが、効果効能を断定的に表現すれば法令違反の可能性があります。広告か否かに関わらず、常に根拠ある表現と法令遵守が求められます。
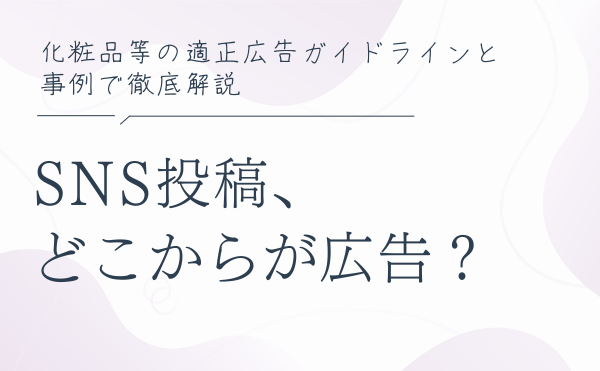
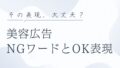
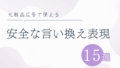
コメント